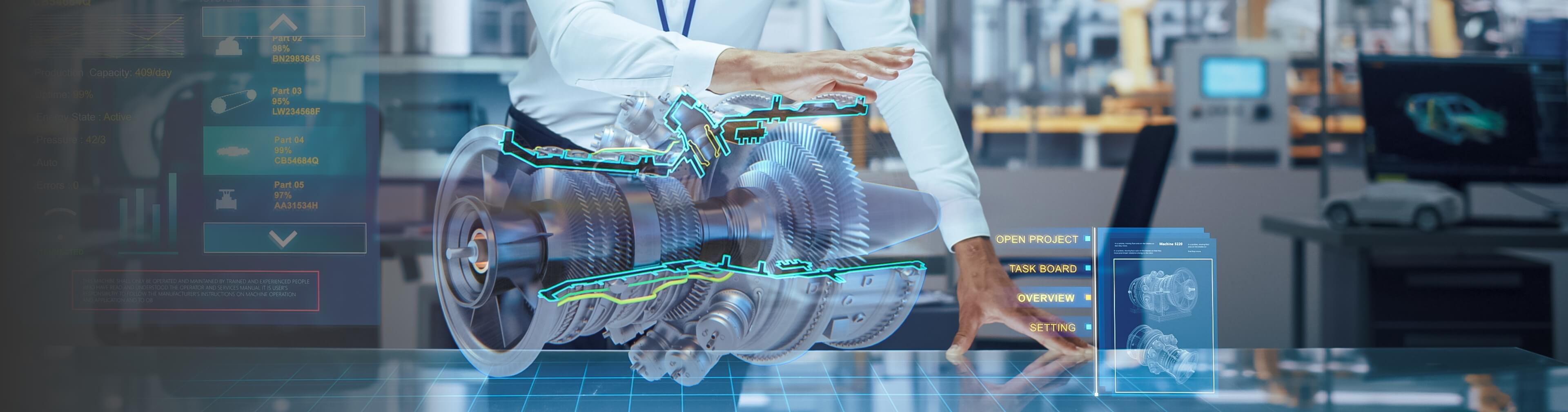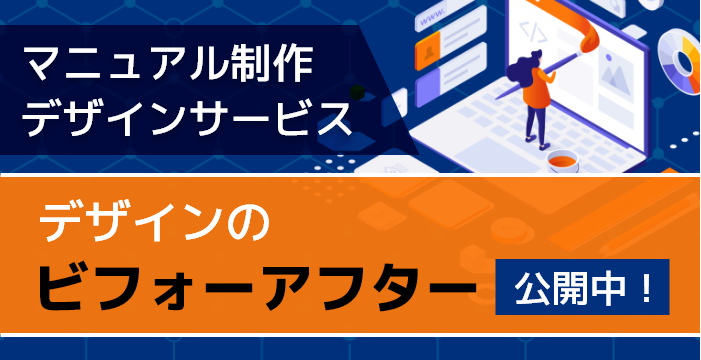なぜ採用はこれほど難しいのか?原因と“今すぐできる”解決策を徹底解説
2025.7.29

「求人を出しても応募が来ない」「良い人材に出会えない」など、多くの採用担当者が頭を悩ませています。採用の難易度が年々高まっていると感じている方も、少なくないはずです。
しかし、なぜ採用はこれほどまでに難しいのでしょうか。
この記事では、採用が難しいと感じる背景にある社会的な要因から、企業側に潜む根本的な原因までを深掘りします。その上で、明日からでも実践できる具体的な解決策をステップごとに解説します。
採用活動に行き詰まりを感じている担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
なぜ今、これほど採用が難しいのか?

採用が難しいと感じる背景には、個々の企業の努力だけでは解決が難しい、社会構造の変化が存在します。マクロな視点から、現在の採用市場で何が起きているのかを正しく理解することが、有効な対策を講じる第一歩となります。
少子高齢化による労働力人口の減少
日本の採用市場が抱える最も根源的な課題は、少子高齢化による生産年齢人口(15歳~64歳)の減少です。総務省の調査によると、日本の労働力人口は長期的に減少傾向にあります。
働く人の数が減っているため、企業間で限られた人材を奪い合う構図になっており、これが採用難易度を押し上げる大きな要因となっています。
参考:総務省 | 生産年齢人口の減少有効求人倍率の高止まり
有効求人倍率とは、求職者1人あたりに何件の求人があるかを示す指標です。この数値が1を上回ると、求職者よりも求人のほうが多い「売り手市場」を意味します。
厚生労働省が発表する一般職業紹介状況を見ると、近年、有効求人倍率は高い水準で推移しており、企業にとっては人材を確保しにくい状況が続いています。特にIT人材などの専門職では、倍率がさらに高くなる傾向にあります。
参考:厚生労働省 | 一般職業紹介状況(令和6年4月分)について働き方と価値観の多様化
かつて主流だった終身雇用や安定志向の価値観は、今や過去のものとなりつつあります。
現代の求職者は、給与や雇用の安定性だけでなく、仕事のやりがい・自己成長の機会・ワークライフバランス・柔軟な働き方(リモートワークやフレックス制度など)といった、より多様な価値観を重視するようになっています。
こうした変化に対応できず、従来型の魅力しか提示できない企業は、求職者から選ばれにくくなるリスクがあります。採用活動では、時代に合った価値観を理解し、それに応えるメッセージや制度設計が求められています。
採用チャネルの複雑化
かつての採用活動は、求人情報誌やハローワークが中心でした。
しかし現在では、総合型・特化型の求人サイトをはじめ、人材紹介サービス、ダイレクトリクルーティング、SNS、リファラル採用など、候補者と接点を持つチャネルは大きく広がり、非常に複雑化しています。
このような状況では、自社に合ったチャネルを見極め、適切に使い分けるための専門的な知識や判断力が求められます。採用担当者にとっては、情報収集や運用の負担が増える一方で、戦略的なチャネル選定が採用成功の鍵となります。
時代に合わせてチャネルを柔軟に活用し、求職者との接点を最大化することが、これからの採用活動には欠かせません。
「採用が難しい」と感じる企業に共通する5つの原因

社会的な要因に加えて、採用がうまくいかない企業には社内に共通の原因が存在することが少なくありません。
ここでは、多くの企業が見落としがちな5つの原因について解説します。自社に当てはまる点がないか、チェックしてみてください。
自社の魅力や強みを言語化できていない
「あなたの会社の魅力は何ですか?」と聞かれて、すぐに答えられるでしょうか。たとえ大手企業のような知名度や待遇がなくても、中小企業にはその企業ならではの魅力が必ずあります。
たとえば、風通しの良い職場環境、社員一人ひとりに与えられる裁量の大きさ、特定分野での技術的な強みなどが挙げられます。
こうした魅力を採用担当者自身がしっかりと理解し、求職者に伝わる言葉で表現できなければ、他社との差別化は難しくなってしまいます。
採用ターゲット像が曖昧になっている
「コミュニケーション能力が高く、主体性のある若手」といった漠然とした人物像をターゲットにしていませんか?採用活動がうまくいかない企業は、求める人物像、いわゆる「採用ペルソナ」の設定が曖昧なケースが多く見られます。ターゲットが曖昧だと、求人票の訴求内容がぼやけてしまい、誰にも響かないメッセージになってしまいます。
その結果、企業とのミスマッチが起きやすくなり、本当に来てほしい人材からの応募が集まらないという事態に陥るのです。
時代に合った採用手法を選択できていない
いまだに、数年前と同じ求人媒体に、同じ内容の広告を掲載し続けていませんか?採用チャネルは年々多様化しており、求職者が情報を得る手段も大きく変化しています。そのため、従来の「求人を出して待つだけ」の方法では、十分な成果を得るのが難しくなっています。
これからは、ダイレクトリクルーティングやSNSの活用など、企業側から積極的に働きかける「攻めの採用手法」が求められます。
自社の採用ターゲットに合った手法へとアップデートし、時代に合った採用活動を進めていきましょう。
選考プロセスが候補者目線ではない
選考プロセスの中で、候補者がどのような体験をするか――いわゆる「候補者体験」への配慮が不足している企業は、意外と多く見受けられます。
たとえば、書類選考の結果連絡が遅い、面接官の態度が高圧的、質問への回答が曖昧など、こうした対応は候補者の志望度を大きく下げてしまいます。
特に優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得る可能性が高いため、少しでも不信感を抱かれると、すぐに選考から離脱されてしまうリスクがあります。
採用成功の鍵は、候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらえる体験を提供できるかどうかにかかっています。
給与や待遇面での競争力不足
仕事に対する価値観が多様化しているとはいえ、給与・休日・福利厚生などの基本的な待遇は、今もなお企業選びの重要な判断材料です。まずは、地域の同業他社や同職種の水準と比較して、自社の待遇が大きく見劣りしていないかを確認しましょう。
もし待遇面の改善が難しい場合でも、働きがいやスキルアップの機会など、他の魅力を具体的に伝える工夫が必要です。
候補者が「この会社で働く価値がある」と感じられるような情報発信が、採用成功への一歩となります。
採用難を乗り越えるための具体的解決策

採用活動がうまくいかないとき、ついテクニックや手法に目が向きがちですが、まず見直すべきは採用戦略の土台です。
小手先の工夫よりも、戦略そのものを整えることが、長期的な成果につながります。
ステップ1:採用戦略の根幹を見直す
小手先のテクニックに走る前に、まずは採用活動の土台となる戦略を見直すことが重要です。
はじめに、採用したい人物像を具体的に描く「採用ペルソナ」を設定します。年齢やスキルだけでなく、価値観や性格、情報収集の方法まで詳細に設定することで、どのようなメッセージが響くのかが明確になります。
次に、3C分析(自社・競合・市場)を用いて、採用市場における自社の立ち位置を客観的に把握します。自社の強みと弱み、競合企業の動向、求職者のニーズを分析することで、戦略の方向性が定まります。
最後に、分析結果を基にEVP(従業員価値提案)を定義します。「この会社で働くと、どのような良い経験や報酬が得られるのか」という企業からの約束を明確にし、採用活動全体の軸とします。
ステップ2:候補者へのアプローチを変える
採用戦略が固まったら、次は候補者へのアプローチ方法を見直しましょう。これまでのように求人媒体に掲載して「待つだけ」のスタイルでは、十分な成果を得るのが難しくなっています。
まずは、求人媒体のスカウト機能を積極的に活用することから始めましょう。
自社の採用ペルソナに合った人材に直接アプローチすることで、応募の質を高めることができます。
さらに、企業側から候補者に働きかけるダイレクトリクルーティングの導入も有効です。
専門サービスを活用すれば、転職をまだ具体的に考えていない潜在層にもアプローチでき、優秀な人材と出会える可能性が広がります。
また、社員の紹介によるリファラル採用もおすすめです。企業文化に合った人材が集まりやすく、定着率が高い上に採用コストも抑えられるため、制度化する価値があります。
そして、SNSを活用した採用広報も忘れてはいけません。会社の雰囲気や社員の働き方を日常的に発信することで、企業のファンを増やし、将来的な候補者層の育成につながります。
ステップ3:選考体験(候補者体験)を向上させる
優秀な人材を惹きつけ、内定辞退を防ぐためには、選考プロセス全体の質を高めることが欠かせません。特に、応募から内定までのスピード感は重要です。選考が長引くと、候補者は他社に決めてしまう可能性があります。
たとえば、書類選考は2営業日以内、面接後の合否連絡は3営業日以内など、社内で明確なルールを設けて、迅速な対応を徹底しましょう。
次に、面接官のトレーニングも重要です。面接は、候補者のスキルや経験を見極める場であると同時に、企業の魅力を伝える「口説きの場」でもあります。面接官が自社の魅力をしっかり伝えられるよう、意識とスキルの向上を図りましょう。
また、選考結果の連絡時には、合否にかかわらず丁寧なフィードバックを心がけることが大切です。特に不採用の場合でも誠実な対応をすることで、企業の印象が良くなり、将来的な応募につながる可能性があります。
さらに、選考の初期段階で「カジュアル面談」を取り入れるのも効果的です。評価を伴わない気軽な対話の場を設けることで、候補者は企業文化への理解を深めやすくなり、ミスマッチの防止にもつながります。
採用手法ごとの特徴を理解する

採用を成功させるには、各手法の特徴を理解し、自社の状況に合わせて組み合わせることが重要です。
ここでは主要な採用手法の特徴を解説します。
求人広告
求人広告は、ウェブサイトや雑誌などに掲載することで、一度に多くの求職者にアプローチできる点が最大のメリットです。比較的低コストで始められるため、初期段階の採用活動にも適しています。
ただし、応募者のスキルや意欲にはばらつきが出やすく、多数の競合企業の求人に埋もれてしまう可能性もあります。
効果を高めるためには、魅力的な求人内容の設計や、掲載先の選定が重要です。
人材紹介
人材紹介は、エージェントが自社の採用要件に合った人材を探して紹介してくれるサービスです。成功報酬型が多いため初期費用を抑えられますが、採用が決まった際の報酬は年収の30~35%が相場と高額になりがちです。
また、採用プロセスをエージェントに依存するため、自社に採用のノウハウが蓄積しにくいという側面も持ち合わせています。
導入する際は、コストと社内の採用力のバランスを見ながら、短期的な成果と長期的な育成の両面を意識することが大切です。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業側からデータベースなどを利用して候補者に直接アプローチする「攻め」の手法です。転職を具体的に考えていない潜在層にもアプローチでき、採用コストを抑えられる可能性があります。
ただし、候補者の選定からスカウト文面の作成、アプローチまでをすべて自社で運用する必要があるため、工数が多く、一定のノウハウも求められます。
導入を検討する際は、社内体制やリソースとのバランスを見ながら、無理のない運用方法を設計することが重要です。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。
社員の紹介だからこそ、企業文化にフィットする人材が集まりやすく、入社後の定着率が高いというメリットがあります。
また、求人広告や人材紹介に比べて採用コストを大幅に抑えられる点も大きな魅力です。一方で、紹介者と候補者の人間関係に配慮が必要なため、運用には慎重さが求められます。
この手法だけで安定的に採用人数を確保するのは難しいため、他の採用手法と組み合わせて活用することが効果的です。
採用活動を成功に導くための3つの心構え

最後に、採用難を乗り越えるために担当者が持つべき心構えを3つ紹介します。
これらの視点を持つことで、日々の活動がより戦略的になります。
採用はマーケティング活動と捉える
現代の採用活動は、商品やサービスを売るマーケティング活動と非常に似ています。
自社という商品を、求職者という顧客に、いかに魅力的に見せて選んでもらうか、という視点が不可欠です。採用ペルソナを設定し、自社の魅力を定義し、適切なチャネルでメッセージを届けるという一連のプロセスは、まさにマーケティングそのものです。
全社で採用に取り組む文化を醸成する
採用は人事部門だけが担うものではありません。経営陣から現場の社員まで、全社が一丸となって「仲間集め」に取り組む文化を醸成することが重要です。
現場社員がリファラル採用に協力したり、面接官として自社の魅力を語ったりすることで、採用力は格段に向上します。採用活動への貢献を評価する仕組みを作ることも有効です。
長期的な視点で採用ブランディングを行う
すぐに成果が出なくても、粘り強く情報発信を続けることが、将来の採用成功につながります。
オウンドメディアやSNSを通じて、自社のビジョンや文化、働く人々の姿を発信し続けることで、徐々に企業の認知度と評判が高まっていきます。
これが採用ブランディングであり、数年後には「あの会社で働きたい」と自然に応募が集まるような状況を作り出すための、最も確実な投資と言えるでしょう。
まとめ
採用が難しい時代であることは事実ですが、その原因を正しく理解し、自社の状況に合わせた対策を一つひとつ実行していくことで、必ず道は開けます。
本記事で紹介した原因分析や具体的な解決策を参考に、まずは自社の採用活動のどこに課題があるのかを見直すことから始めてみてください。
戦略的な視点を持ち、粘り強く取り組むことで、採用成功への道が確実に開けていきます。
エンジニアとして働きたい人と、エンジニア不足にお困りの企業様をつなぐ
BREXA Technologyは、エンジニアとしてのキャリアを志す人材と、IT人材不足に課題を抱える企業様をつなぐ架け橋として、さまざまな業界における人材課題の解決と働き方改革の推進を支援しています。
慢性的な人手不足や、従業員一人ひとりへの過度な業務負担といった現場の課題に対し、当社は「人」と「テクノロジー」を融合させたソリューションをワンストップでご提供。貴社のニーズに最適化された先端技術と人材をご提案いたします。
人材戦略のパートナーとして、ぜひBREXA Technologyをご活用ください。